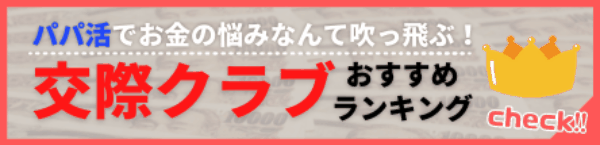目次
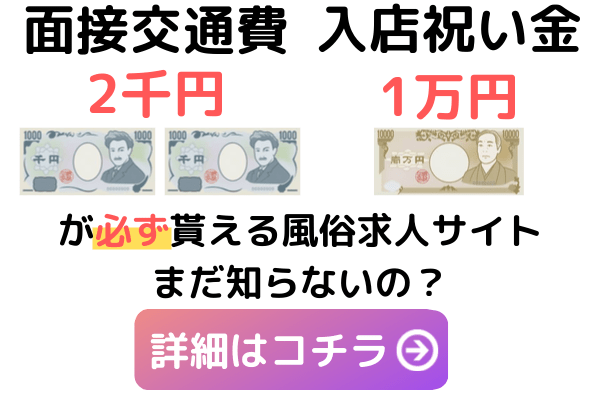
ソープランドの原点となった吉原遊郭と遊女
現在では本番ができる風俗店であるソープランドはかつて日本各地にあった遊郭、赤線の地域に今でも店を構えています。
ソープランドはデリヘルのようにどこでも出店できるものではなく、新規の開業もなかなか難しいようです。
※法律に基づいた正規店の新規開業がほぼ不可能なので、現在では店舗の商権は高額で売買されています。
このページでは、ソープランドの原点である『遊郭』について解説しています。
江戸時代を代表する文化のひとつですので、膨大な量の資料や情報がありますが、このページではそこまで難解な情報は扱いません。
1遊女(ゆうじょ)とは?

遊女(ゆうじょ)とは、もともとは神様に使える巫女(みこ)や高貴な身分の男性の周囲にいる踊り子や歌い手のことを意味します。
遊女(ゆうじょ、あそびめ)
遊郭や宿場で男性に性的サービスをする女性のことで、娼婦、売春婦の古い呼称。「客を遊ばせる女」と言う意味が一般的である。
引用:ウィキペディア
仕事や彼女達が持つ特殊技能の中のひとつとして性技があったとされています。
昔の人はセックスを神様と通じる方法と考えていたようで、現在とは考え方が全く違います。
このように、セックスをただの生殖以外にも意味があるという考え方は日本だけでなく、世界中の古代文明で見られる傾向です。
2行脚(あんぎゃ)とは?
日本では遊女は全国を行脚(あんぎゃ)しながら自分の芸(歌、踊り、楽器など)を披露し、売る芸事の中のひとつとして性の技術をお客さんに売るようになりました。
行脚(あんぎゃ)
僧が諸国をめぐり歩いて修行すること。転じて、方々を(徒歩で)旅行すること。
引用:ウィキペディア
これが売春婦の起源とされています。
3全国津々浦々(ぜんこくつつうらうら)とは?
遊女が全国津々浦々(ぜんこくつつうらうら)にいる状況が長く続いたようですが、この状況に終止符を打ったのがあの豊臣秀吉で、1584年に大阪に日本全国の遊女を集めます。
全国津々浦々(ぜんこくつつうらうら)
国中のいたるところ、全国各地、国内のあらゆる地域といった意味の語。
引用:日本語表現辞典
これが遊郭(ゆうかく)のはじまりです。
4遊郭(ゆうかく)とは?
遊郭は現在風に言うと、公認された風俗店が密集する地域と考えてください。
遊廓(ゆうかく)
公許の遊女屋を集め、周囲を塀や堀などで囲った区画のこと。
引用:ウィキペディア
遊郭のはじまりと変化については、西暦でページ下部にまとめてあります。
遊女以外にも旅館で売春する「飯盛女」や「夜鷹」と呼ばれる女性達
江戸時代には旅館・旅籠に
- 「飯盛女(めしもりおんな)」
- 「食売女(めしうりおんな)」
- 「宿場女郎(しゅくばじょろう)」
と呼ばれる女性がいました。
飯盛女(めしもりおんな)または飯売女(めしうりおんな)は、近世(主に江戸時代を中心とする)日本の宿場に存在した私娼である。宿場女郎(しゅくばじょろう)ともいう。
江戸時代、娼婦は江戸の吉原遊郭ほか、為政者が定めた遊郭の中のみで営業が許されていたが、飯盛り女に限っては「宿場の奉公人」という名目で半ば黙認されていた。飯盛女はその名の通り給仕を行う現在の仲居と同じ内容の仕事に従事している者も指しており、一概に「売春婦」のみを指すわけではない。
また「飯盛女」の名は俗称であり、1718年以降の幕府法令(触書)では「食売女(めしうりおんな)」と表記されている。
引用:ウィキペディア
彼女達は旅館に宿泊する男性に対して、食事や掃除・選択などの身の回りの世話をするだけでなく、セックスもサービスとして提供していました。
幕府公認の遊女と比べるとかなりアンダーグラウンドな職業でしたが、値段の安さから人気があったようです。
品川などの当時の主要交通路にある宿舎には1,000人を超える飯盛女が働いていたと言われています。
他にも現在の言葉で表すなら「たちんぼ」の「夜鷹(よたか)」と呼ばれる私娼(ししょう)の女性達など、非公認とはいえ風俗に関連する職業の女性はたくさんいたようです。
私娼(ししょう)
娼婦に公に営業の許可をあたえる制度がある場合、娼婦のうち、公の営業許可を得ていない娼婦をいう。公(おおやけ)に営業を許された公娼に対する。
引用:ウィキペディア
どんな女性が遊女になっていたのか?
- 貧しい農家の「口減らし」目的で遊郭に売られた女性
(食べ物が無いので育てる家族を減らすこと) - 貧しい武家がお金を稼ぐために売られた女性
- 遊郭で生まれ育った女性
などが遊女になっていったと言われています。

遊女は10年契約だったと言われていますが、実際に10年以上働ける女性は稀だったと言われています。
吉原でお客をとれるようになるまでは10年のうちに入りませんので、お客をとれる17歳になってから27歳になるまでが年季(契約期間)です。
10年という契約期間内に借金返済ができなかった場合
10年間一生懸命お客さんをとって働いても借金の返済が完了しない場合は、
- そのまま位の低い遊女として続行
- 「縫子(ぬいこ)」「飯炊き(めしたき)」と呼ばれる遊女ではなく裏方
などの仕事につきました。
また吉原だけで多い時期には7,000人から8,000人の遊女がいたとされています。

遊女に付けられていたランク
- 大夫(だゆう)・花魁(おいらん)
- 格子女郎(こうしじょろう)
- 局(つぼね)
- 端女郎(はしじょろう)
- 切見世女郎(きりみせじょろう)
上から高級な遊女とされています。
その時代によって他にもランクがあったりして呼ばれ方も変わります当然、花魁になると遊ぶために男性が支払う金額も膨大な金額になったようです。

一回の酒宴(しゅえん)は現在の貨幣価値に換算すると、数百万円〜1千万円くらいだったようです。
それだけのお金を使っても花魁が男性を気に入らなればお相手してもらえなかったのです。
高級風俗で働く女性というよりは、一種のアイドル=偶像のようなものとして花魁は存在していたのでしょう。
当時の指名制度は永久指名が当たり前
ちなみ男性は一人の遊女と遊んだら他の遊女と遊ぶことが禁止されていたようです。
現代風に言うと永久指名制です。
同時に他の遊女と遊んだりしていたら大変な罰を受けたとか。。。
これは遊女同士が嫉妬して喧嘩したりするのを防ぐための手段だったという説もあります。
最高ランクの遊女「花魁(おいらん)」「大夫(だゆう)」はトップモデル

花魁には禿(かむろ)と呼ばれる10歳前後の少女が身の回りの世話をする係としてつき、豪勢な服を着て、男性だけでなく女性からも憧れの目で見られていました。
浮世絵の題材にもなり、有名な花魁の髪型は江戸中で流行するなど、アイドルやファッションリーダーのような役割も果たしていました。
花魁は○○大夫と呼ばれ、歌舞伎師役者のように襲名されていました(血のつながりはありません)。
- 「吉原の高尾大夫」
- 「島原の吉野大夫」
などは講談のネタになったりするなどして現在でも知名度は高いです。
花魁になる女性は幼少期から英才教育が当たり前
容姿が優れているだけでなく、花魁になるような女性は幼い頃から
- 漢詩・和歌などの古典芸能
- 書道
- 茶道
- 香道
- 華道
- 琴・三味線
などを芸事をみっちり仕込まれています。
※「もちろん花魁によって得意なジャンルや不得意なジャンルはあったはずです」。
当時でも、服やお化粧などを含む外見・教養共に庶民とは別格の存在だったのです。
このような教養以外にも夜の床でのテクニックも幼い頃から仕込まれます。
だからと言って、「花魁はもの凄くお金持ちだったか?」というとそんなこともなかったようで、
- お店に支払うお金があったり
- 自分の周囲にいる女性達の生活費やお小遣い
- 自分の衣装や化粧代
などが自費だったので、お金に余裕があった人は少なかったようです。
当時の避妊方法と性病予防方法

コンドームについては、動物の皮などを袋状にしてコンドーム替わりに使用していたという説がありますが、定かではありません。
妊娠については、当時避妊に効果があるとされている方法を採用していました。
方法とは、セックスの前に「和紙」を小さく折りたたんで膣に入れることです。
もちろんこんなもので避妊できるはずもなく、妊娠する遊女はたくさんいました。
高級遊女は事前に漢方などの薬を飲んでいたという説もありますが、江戸時代のことなので本当に避妊に有効的な漢方薬があったとも思えません。
当時の万が一妊娠してしまった場合の対処法
妊娠したら当然仕事ができなくなります。
仕事ができなくなればお金が稼げなくて困ります。
なので、水銀を含む薬を飲んで死産させるなど惨い方法をとっていました。
もちろん水銀は毒なので子供だけでなく遊女も一緒に亡くなることもたくさんあったはずです。
梅毒によって顔がただれたりする描写も当時の文献にはあります。
HIVはまだ無かったにせよ抗生物質が無い以上、性病に感染したら放置なので、病気は進行するのみです。
当時の遊女の平均寿命が22歳と言われていますので、その環境は想像を絶するものだったと思います。
遊女を辞めるには「借金返済」か「身請け」してくれる男性を見つける
遊女は借金を返さなければ遊郭から出れません。
その借金を払ってくれる男性が運良く表れることを「見受け(みうけ)」「身請け(みうけ)」と言います。
他にも、落籍(ひか)されるという表現があります。
身請(みうけ)
芸娼妓などの身の代金(前借り金)を支払い、約束の年季があけるまえに、稼業をやめさせることである。身請ののち、自分の妻、また妾にすることもある。落籍(ひか、らくせき)ともいう。
引用:ウィキペディア
花魁の引退は、お店の営業に大きな損失を出すために現在の価値で1億円近く払った男性もいるということなので花魁の凄さがわかります。
大金のお金を使用して見受けしてもらってもその男性と結婚できると決まっているわけではなく、愛人のような立場で囲われたりすることも多かったようです。
ですが、幸せな形で花魁を引退して遊郭から出れる女性は少なく、だいたいの女性が病気などで若くして亡くなるか、遊女を引退後も遊郭の中で仕事をするなどして生涯を終えていたようです。
吉原から逃亡する事を「足抜け」と呼ばれる
当時そこまで数は多く無いようですが、吉原から脱走するような形で離れる女性もいました。
脱走のことは「足抜け(あしぬけ)」と呼ばれていました。
本来支払わなければならない借金を返済せずに逃げる行為なので当時としても決して良い行為とは思われていなかったでしょう。
遊郭の歴史まとめ
- 1584年
豊臣秀吉によって大阪の道頓堀川北岸に遊女が集められ、遊郭ができる - 1589年
京都柳町に遊廓ができる - 1612年
徳川幕府によって日本橋人形町付近に吉原遊廓ができる - 1617年
現在の日本橋人形町あたりに遊郭・葭原(よしわら)ができる。
約220メートル四方の範囲で区画されていた地域に店が構えられてた。
名前の由来は、当時誰も住んでいなくて葦(アシ)ばかりの土地の原っぱ(原)の「あしはら」が「あし=よし」に変わったとされている。
小田原出身の庄司甚右衛門が幕府に嘆願して公式に遊郭が設置された。 - 1627年
大阪に新町遊廓(しんまちゆうかく)が設置ができる - 1641年
京都柳町の遊廓が朱雀野付近への移転して「島原遊郭」ができる - 1656年
明暦の大火によって吉原が浅草に移動、新吉原と呼ばれる - 1869年
大阪に松島遊郭ができる - 1871年
札幌に薄野(すすきの)遊郭ができる - 1872年
明治政府によって芸娼妓解放令が発令される - 1946年
GHQの指令により遊郭は廃止され赤線(あかせん)と名前を変えて営業 - 1956年
売春防止法が成立 - 1958年
売春防止法が施行。
これによって赤線=吉原遊郭が完全に消滅、トルコ風呂に名前を変えて営業 - 1984年
トルコ大使館からの抗議を受けてトルコ風呂という名前が現在でも使われるソープランドに変更される
吉原で起きた火事の歴史
- 1656年
明暦の大火 - 1911年(明治44年)
吉原大火 - 1923年(大正12年)
関東大震災で全焼
小説や舞台の題材になっていますが、吉原は家事が多い地域でした。
放火など人為的(じんいてき)なものが多かったようです。
それでもすぐに復活して営業していたようなので、逞しさ(たくましさ)に驚きます。
現在でも使用される吉原で生まれた言葉
吉原その独特の世界からか吉原ならではの言葉が生まれました。
現在でもその名残りがあり、「お茶を挽く(ひく)」などは頻繁に今の風俗業界でも使われます。
「お茶を挽く」とは、お客さんが一人も入らなかったことで、この言葉は実際に吉原の遊女はお客さんから指名が無かった時にお客さんに出すお茶っ葉を石臼(いしうす)で挽いていた(ひいていた)ことから使われるようになりました。
この記事を読んだ人におすすめの記事
https://curios.wpx.jp/8.html
https://curios.wpx.jp/sinjukuso.html


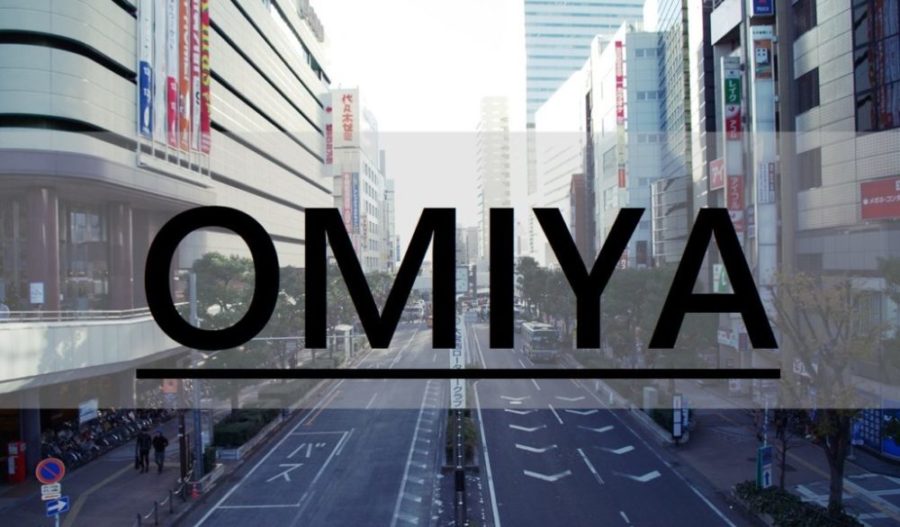
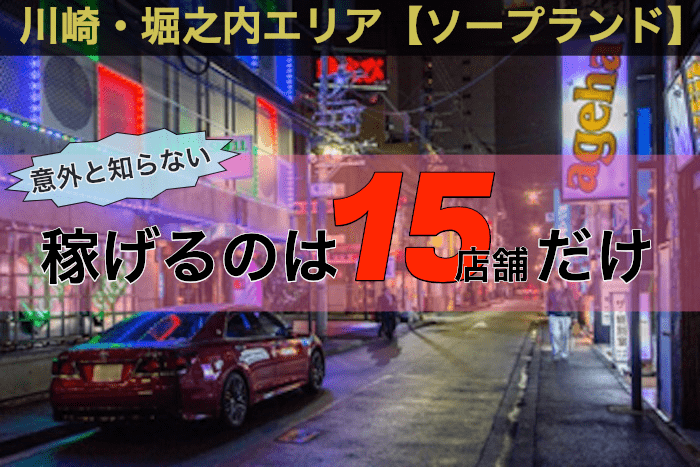








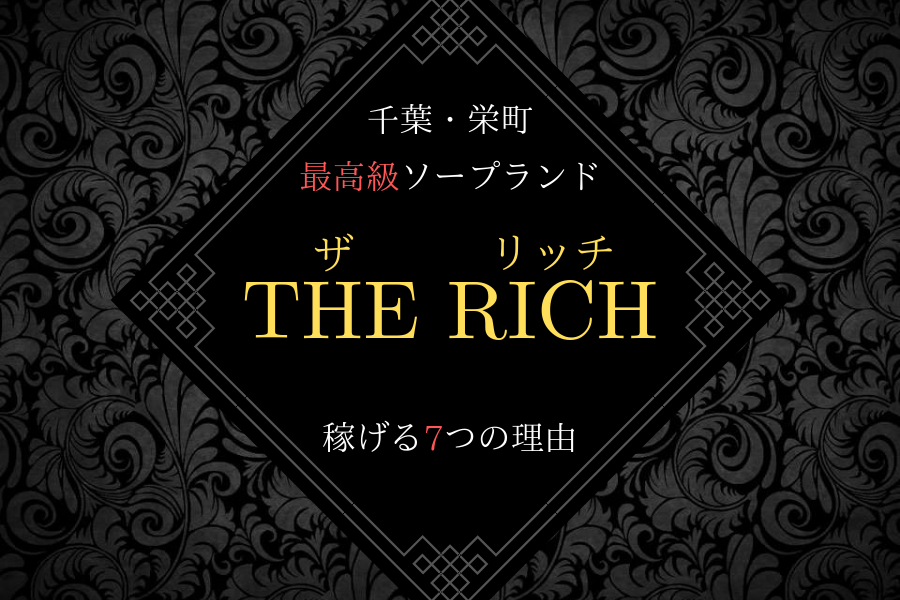



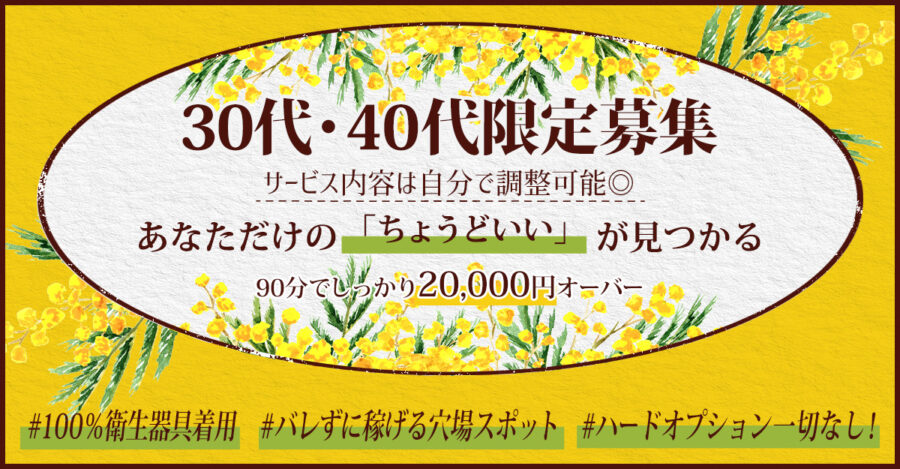






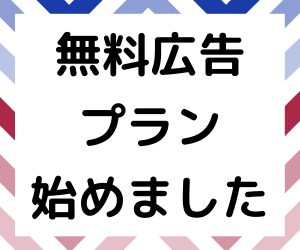
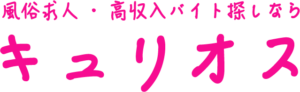 キュリオスは高収入・副収入を得たい女性のための情報メディアです。今の収入では満足できない女性や、高収入バイトを今から始めようと思っている女性などの手助けになれば幸いです。
キュリオスは高収入・副収入を得たい女性のための情報メディアです。今の収入では満足できない女性や、高収入バイトを今から始めようと思っている女性などの手助けになれば幸いです。